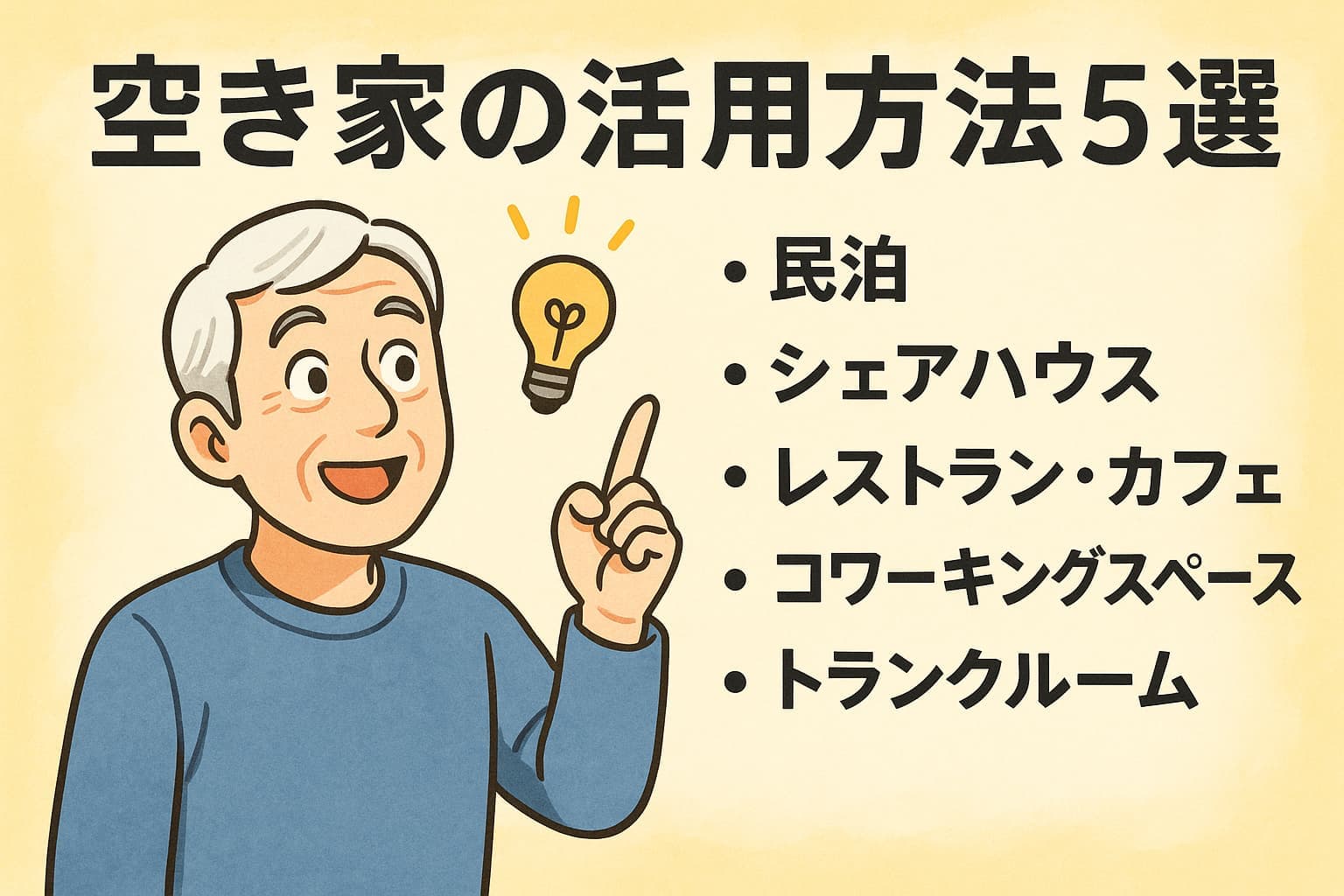近年、全国的に空き家の活用が注目を集めています。 相続した実家や使わなくなった物件を「そのまま放置していてもったいない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の活用方法について、具体的な事例とともにご紹介していきます。
<<cta-contact-general>>
空き家の活用方法5選

空き家の活用方法には、実にさまざまな選択肢があります。
中でも特に注目されているのが、以下のような使い方です:
- 民泊
- シェアハウス
- レストラン・カフェ
- コワーキングスペースやシェアオフィス
- トランクルームや倉庫
今回は、これら代表的な空き家の活用法についてわかりやすくご紹介していきます。
民泊
観光地に近い立地の空き家では、民泊として活用することで高い収益が期待できます。
特に湘南エリアのような観光地では、海の近くや風情のある古民家が観光客に人気です。
地域の魅力を生かした宿泊施設として運営することで、地域活性化にも貢献できる活用方法といえるでしょう。
ただし、旅館業法や建築基準法などの法律や規制をしっかりと理解し、適切に運営する必要があります。
近隣住民への配慮も欠かせませんし、清掃や管理の手間もかかることを理解しておきましょう。
許可申請や運営ノウハウが必要なため、初心者には少しハードルが高い活用方法かもしれません。
民泊の事例:a OISO la 相模湾を一望する小さなVilla

引用元: https://www.cera.co.jp/casestudy/detail/id=4572
神奈川県中郡大磯町にある民泊施設「a OISO la」は、築50年の平屋をフルリノベーションした事例です。
空き家だった建物にサウナやおしゃれなリビング、相模湾を一望できるバルコニーを設置し、魅力的な宿泊施設に生まれ変わりました。
古い建物の良さを生かしながら現代的な設備を取り入れることで、多くの宿泊客に愛される施設となっています。
参考: https://www.instagram.com/a.oiso.la_1965/
シェアハウス
複数の入居者から家賃収入を得られるシェアハウスは、若者層をターゲットにした空き家活用方法として人気です。
一人暮らしよりも家賃を安く抑えられるため、学生や社会人に需要があります。
個室とリビングやキッチンなどの共用部分を分けることで、プライバシーを保ちながらコミュニティを形成できる住環境を提供できます。
運営する際は、入居者同士のトラブル防止や共用部分の清掃管理、入退去の手続きなど、細かな管理業務が発生することを理解しておく必要があります。
また、建築基準法や消防法などの法的要件を満たす必要があるため、事前の確認と対応が重要です。
シェアハウスの事例:鎌倉雪ノ下のシェアハウス

引用:https://hello-renovation.jp/renovations/12050
鎌倉市雪ノ下にあるシェアハウスは、JR鎌倉駅の東側に位置し、ていねいな暮らしを楽しむ女性のための施設として運営されています。
プライベートをじっくり・ゆっくり過ごせる個人空間と、人とゆるくつながれる共用空間のバランスが絶妙に設計されています。
ちょっと時間をかけて自分でつくってみる、その過程を楽しむ、そんな女子たちのための場所です。
参考: https://hello-renovation.jp/renovations/12050
カフェ・レストラン
カフェや喫茶店などの軽飲食店から、本格的な料理を提供するレストランまで、幅広い用途で空き家を活用できます。
特に古民家をリノベーションしたカフェは、風情のあるデザインが人気を集めています。
地域住民の憩いの場として機能することで、コミュニティづくりができるかもしれません
飲食店営業許可や建築基準法への適合など、必要な手続きは確実に行う必要があります。
旅館業などと比較して、各種規制のハードルが低く、リフォームをある程度自分で対応すれば、開業資金も比較的少なく抑えられる点も魅力です。
カフェの事例:ATELIER SANTi(アトリエ サンティ)

引用: https://co-trip.jp/article/585313
JR東海道線大磯駅から徒歩7分の立地にある「ATELIER SANTi」は、築100年以上の古民家をリノベーションしたカフェです。
歴史を感じさせる建物の魅力を最大限に活かしながら、現代的な飲食店として生まれ変わりました。
地域の人々や観光客に愛される場所として、空き家活用の成功例と言えるでしょう。
参考: https://www.instagram.com/atelier_santi/
コワーキングスペース・シェアオフィス
オープンな環境で仕事ができる場所として「コワーキングスペース」の注目が高まっています。
レンタルオフィスやシェアオフィスなど、類似サービスの中でもコワーキングスペースは空き家活用時に初期費用を抑えやすい特徴を持っています。
リモートワークの普及により、都市部だけでなく郊外・地方でもニーズが見込まれる可能性が十分に考えられます。
フリーランスや起業家、地方移住者などが利用することで、地域の新しいビジネス拠点としても機能します。
Wi-Fi環境や電源の確保、防音対策など、働く環境としての基本的な設備投資は必要ですが、住居系の活用と比べて法的制約が少ない点も魅力です。
コワーキングスペースの事例:coworking space「ダイクマチ」

埼玉県川越市にある「ダイクマチ」は、古い建物をコワーキングスペースとして活用した事例です。
地域のクリエイターや起業家が集まる場所として機能し、新しいビジネスやコミュニティが生まれる拠点となっています。
古い建物の魅力を活かしながら、現代の働き方に対応した施設として注目を集めています。
参考:https://koedo.info/180209daikumachi/
トランクルーム・貸倉庫
初期投資が比較的少なく済むため、空き家活用の入門編として人気があります。
大規模なリフォームをせず、簡易な棚の設置や防犯対策程度で始められることが多いため、コストを抑えた活用ができます。
居住用途に比べて規制が緩やかで、賃貸や民泊と比べ、消防・衛生などの法的ハードルが低めです。
住宅用に不向きな空き家でも活用しやすいのがメリットといえるでしょう。
立地に左右されにくいニーズがあり、駅近でなくても、地方や郊外でも「収納スペースがほしい」というニーズは根強いため、比較的需要が見込めます。
管理の手間が少なく、入居者の入れ替わりや設備の維持管理が少ないため、オーナー側の手間やリスクが少なく、遠方からでも運営しやすいです。
空き家を活用するメリット

空き家をそのまま放置していると、固定資産税を払い続けるだけの「負担」になってしまいます。
しかし、適切に活用することで、その負担を軽減し、さらには収益を生み出すこともできます。
空き家活用の具体的なメリットについて見ていきましょう。
収入が得られるため、固定資産税や維持コストを軽減できる
空き家を賃貸として貸し出すことで、毎月安定した収入を得ることができます。
これまで払うだけだった固定資産税が、家賃収入によって相殺され、プラスになることもあります。
適切な活用により資産価値が向上することも期待できるため、将来的な売却時にも売りやすくなる可能性があります。
また、近年空き家を放置し続けると行政から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されしまい、固定資産税が上がってしまう空き家も多いです。
しかし、空き家を活用していればそのようなリスクを防ぐことができます。
事故や災害・近隣トラブルを回避できる
空き家が使われることで、定期的な使用や清掃により劣化を防ぐことができます。
通風・通水が行われることで、湿気やカビの発生を防ぎ、老朽化の進行を抑えられます。
人の出入りがあることで防犯効果も高まり、不法侵入や不法投棄などのリスクを減らせます。
近隣住民にとっても、管理されている建物があることで安心感につながります。
放置による建物の倒壊リスクや、雑草の繁茂による環境悪化なども防ぐことができ、地域全体の安全性向上に貢献できます。
地域社会への貢献ができる
空き家を活用することで、地域に新しい価値を提供できます。
民泊やカフェとして活用すれば、観光客を呼び込み地域経済の活性化に貢献できます。
シェアハウスやコワーキングスペースなら、移住者や起業家を受け入れる場として機能し、地域コミュニティの活性化につながります。
地域の人々が利用できる施設として活用することで、コミュニティの拠点としての役割も果たせます。
空き家を活用する際に気を付けるべきポイント・デメリット
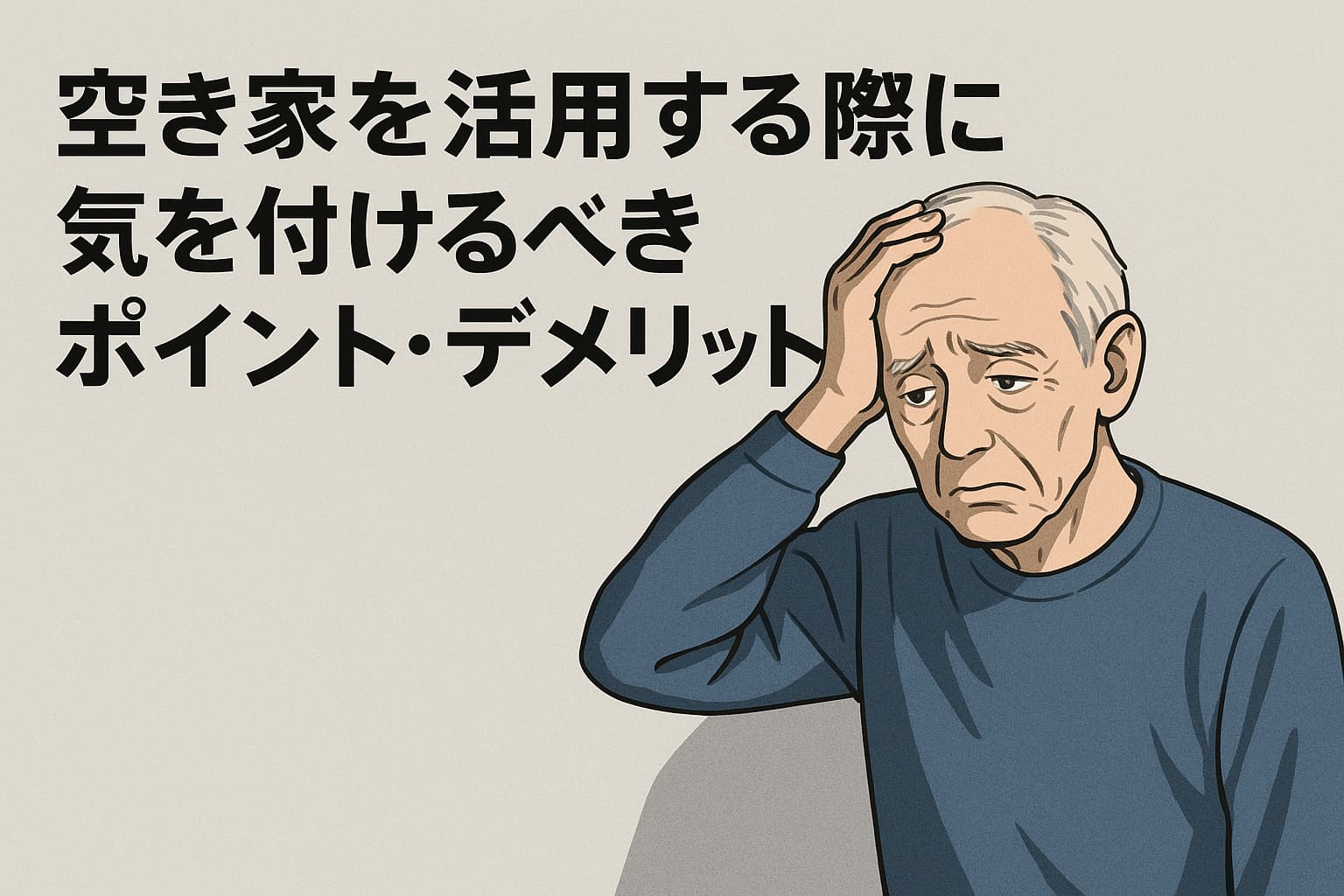
空き家活用には多くのメリットがある一方で、注意すべきポイントやデメリットも存在します。
大前提として、とにかく空き家を放置しないことが重要です。
放置による税負担の増加、地域の治安悪化や不法投棄のリスクなど、時間が経つほど問題は深刻化します。
早期のアクションが求められる理由を理解し、適切な対策を講じることが大切です。
デメリットを理解した上で、それらを解決する方法を見つけることが成功の鍵となります。
貸し出しに時間がかかることが多い
空き家を賃貸物件として貸し出す場合、借り手がすぐに見つかるとは限りません。
特に老朽化が進んでいる物件ほど、借り手が付きづらい傾向があります。
立地や建物の状態、家賃設定などによって、入居者が決まるまでに数ヶ月から1年以上かかることもあります。
その間も固定資産税や管理費用は発生し続けるため、収支計画をしっかりと立てておく必要があります。
借り手が見つからない期間が長引くほど、オーナーの負担は大きくなってしまいます。
家の修繕・メンテナンスの費用がかかる
所有者として、空き家を貸し出すために必要な修繕を行う責任があります。
古い建物ほど、水回りや電気設備、屋根や外壁など、様々な箇所で修繕が必要になることが多いです。
リフォーム費用が数百万円になることもあり、初期投資として大きな負担となる場合があります。
また、入居者が住んでいる間も、設備の故障や不具合に対応する必要があり、継続的な費用が発生します。
これらの費用を事前に見積もっておかないと、収支が合わなくなってしまう可能性があります。
賃貸に出す場合は大家として管理コストがかかる
賃貸物件として貸し出す場合、大家として様々な管理業務を行う必要があります。
入居者とのやりとりや契約手続き、家賃の回収など、継続的な事務作業が発生します。
近隣へのトラブル対応や苦情処理なども大家の責任となり、時間と労力が必要です。
特に遠方に住んでいる場合、現地での対応が困難になることもあります。
管理会社に委託することもできますが、その場合は管理費用が発生し、収益性が下がってしまいます。
相続した空き家を上手に活用したいけど何から始めればいい?
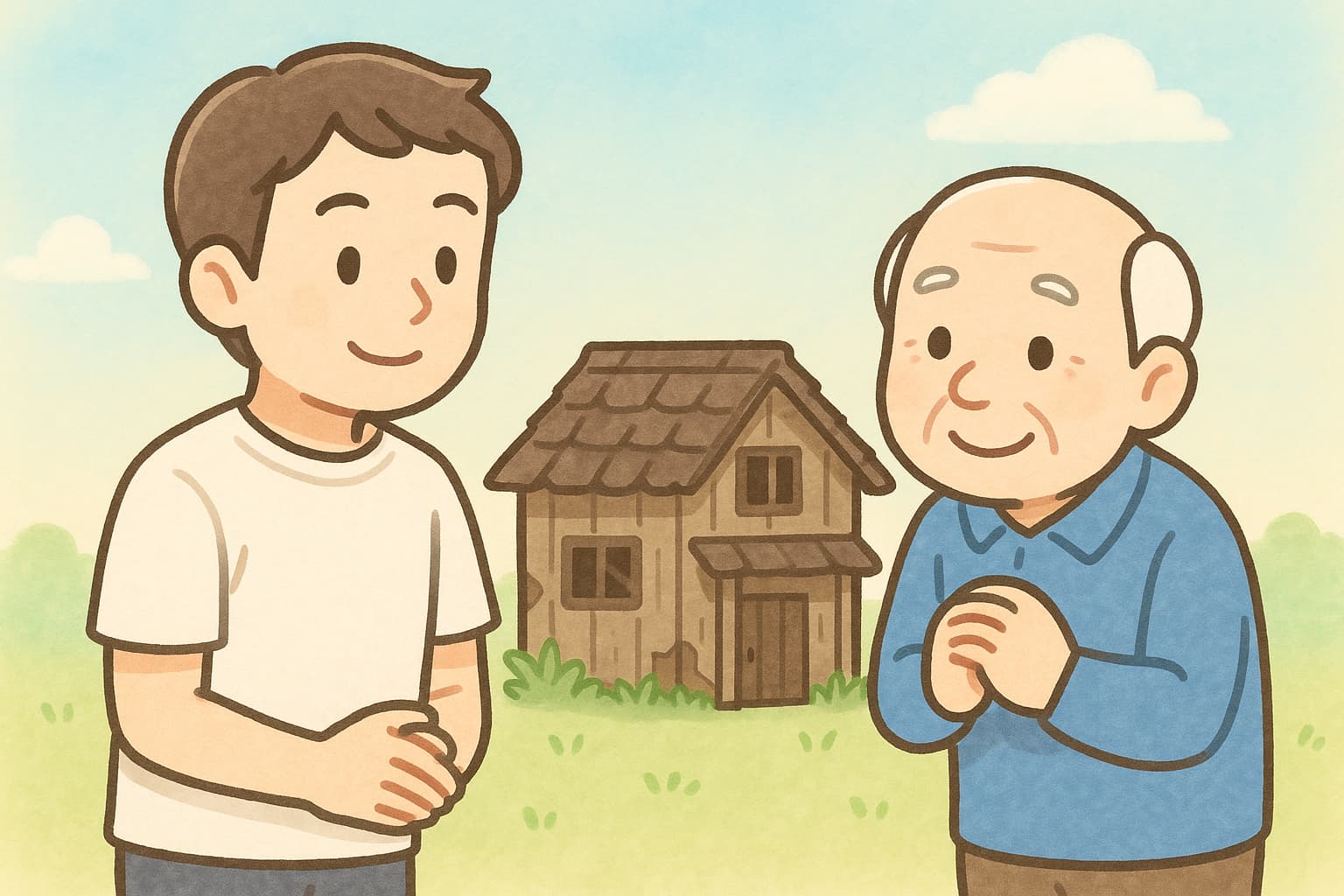
相続した空き家の活用を考えているものの、「何から手をつけたらいいかわからない」という方も多いでしょう。
固定資産税だけを払い続けている状況から抜け出したいと思いながらも、具体的な行動に移せずにいるのは自然なことです。
まずは現在の状況を整理し、無理のない範囲で進められる方法を見つけることが大切です。
自分で活用することを検討してみる
これまでご紹介した通り、民泊、シェアハウス、カフェ、レストラン、コワーキングスペース、倉庫など、さまざまな活用方法があります。
まずは所有している空き家の立地や建物の状態、周辺環境などを考慮して、どのような活用方法が適しているかを検討してみましょう。
ただし、自分で活用する場合は法的手続きや初期投資、継続的な管理業務など、多くの負担が発生することを理解しておく必要があります。
時間と労力をかけられる方には良い選択肢ですが、「面倒な手続きはしたくない」という方には向かない方法かもしれません。
空き家の専門家に相談する
自分で空き家の活用方法を考えるのは大変な作業です。
法律や税制、建築基準など、専門的な知識が必要な分野も多く、一人で対応するには限界があります。
そのような場合は、空き家活用の専門家に相談することをおすすめします。
いくらインターネットで調べても、一般的な知識しか得られず、自分の空き家にフォーカスした解決策を見つけることは難しいでしょう。
空き家の状態や地域の特性に合った活用法を一緒に模索してくれる専門家に相談することがよいでしょう。
専門家の知識と経験を活用することで、リスクを最小限に抑えながら最適な活用方法を見つけることができます。
コストをかけずに空き家を活用するなら、「湘南空き家ラボ」がおすすめ
空き家を借り受けて活用する「湘南空き家ラボ」のサービスは、これまでご紹介したデメリットや注意点を解消する画期的なサービスです。
建物はそのままの状態でお預かりするため、片付けや清掃の手間は一切かかりません。
また、リフォーム費用はこちらが負担するため、オーナー様の初期投資はゼロで始めることができます。
家賃収入が得られる仕組みになっており、これまで「払う一方」だった固定資産税の負担を軽減できます。
さらに、空き家を活用したい方を募集し、入居者とのやりとりもすべて「湘南空き家ラボ」が対応するため、管理の手間がかかりません。
建物の管理や近隣トラブルへの対応も安心してお任せいただけるため、遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
まずはお気軽にご相談ください
初回相談は無料でお客様の状況に合わせて具体的なプランを提案いたします。
空き家の状態や立地、ご希望などをお聞かせいただければ、最適な活用方法をご提案できます。
フォームでの問い合わせもできますので、ぜひお気軽にご相談ください。
<<cta-contact-general>>